
コーネル大学(アメリカ合衆国 イサカ)
2012年7月15日~2012年9月15日(63日間)
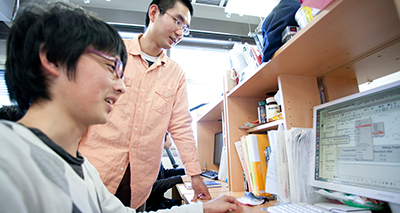
本派遣では、DNAハイドロゲルの中でも特にハイブリダイゼーション(二重らせん化)のみによって構造化するゲル(H-gel)にターゲットを絞って研究に取り組んだという浜田先生。その実施プロセスは、「基礎的な設計指針・作製方法の理解に向けて、すでに報告されている構造の作製」→「DNA論理回路を組み合わせて使用するのに適したモチーフ設計」→「前者を利用して、論理回路を組み込んだDNAハイドロゲルの設計・作製」と、DNAハイドロゲルの理解からそれを踏まえた独自の構造設計・作製へとステップアップしていくように創意工夫がなされました。
「今回はハイブリダイゼーションのみによるゲル構造の基本的な特性を調べ、その知見をふまえて設計することで、これまでのDNAハイドロゲルの中でも最もシンプルな構造を持つ、1種類の配列からゲル化する新規モチーフ構造を実現しました。また、ここで考案した設計指針を利用することで、室温で混合するだけでゲル化が可能、もしくは低濃度でもゲル化可能といった各種特徴を持つDNAモチーフを設計・作製することができました。さらには、これらのゲルを拡張することで、本派遣の主目的であるDNA論理回路を組み込んだDNAハイドロゲルのプロトタイプをつくり、実験により動作を確認しました」。これらの大きな成果はLuo研究室の知見と、それを礎としたディスカッションなくしては生まれ得なかったものという浜田先生。そして研究に注がれていた視点はまた、独特の学生指導の姿を捉えていました。
これは米国という国の成り立ちや歴史、文化的背景に起因するもので良し悪しの問題ではないのですが、と前置きの上で続けられました。「よく知られているように米国では教員と学生の上下関係が非常にフラットです。ですからトップダウン型の教育は成立しにくく、教員は指導するのではなく、助言を与える“アドバイザー”としての役割が強いのです。このような研究室運営ができる理由のひとつには、学生一人ひとりが研究をやり遂げようという意思がとても強く、ある種のプロフェッショナリズムが浸透しているからだと感じました」。そしてさらに驚かされたのがプロジェクトの進め方だと浜田先生は言います。「研究の立ち上げ時は、大きな枠組みだけを示し、そこから先は学生の自主性に任せるという形をとっているのも印象的でした。学生からの提案内容が、研究室の方針に沿うものであるかどうかの最低限の判断は行いますが、それ以外、教員は積極的な介入を行いません」。「もちろん、教員・学生双方が納得するまで民主的に話しあわなければいけないという意味では、即応性に乏しい仕組みかもしれませんし、また教員としては忍耐を要するやり方といえるかもしれませんが(笑)、その分、自分たちがつくり上げる研究室であるという学生たちの自覚が芽生えます」。
しかし、“米国式”をそのまま“輸入”して機能させるのは困難、と考える浜田先生。「もちろんきめ細かな個別指導など、日本にも良いと思われる点が多々あります。それぞれの長所をできる限り融合させていくことを模索しなければならないでしょう。私は現在、指導場面においては上下関係を前提としたものではなく、学生との話し合いにより、目的を納得してもらい、具体的な手順を決めていくよう心掛けています。これにより学生自身の工夫や新しいアイディアの種を引き出すことにもなりますし、何よりも能動的に発言していこうという意欲を高めることにつながっていると実感しています」。「研究の楽しさを見出し、それをドライビングフォースとしてほしいですね。今も昔も、私がそうであるように」――先輩として、アドバイザーとして、指導者として、そして何よりも研究者として、浜田先生の八面六臂の活躍が続きます。
本サイトに掲載されている個人情報は、本人の了解のもとに本サイトに限り公開しているものです。よって第三者がそれらの個人情報を別の目的で使用することや、本サイトの無断転載は固くお断りいたします。