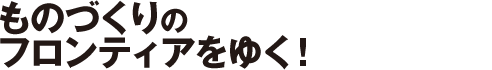21世紀のキーテクノロジー・ナノ医工学の未来を拓く。
ナノスケールで取り組む研究開発。生命現象を工学的に捉える。
「ナノ医工学」とは、ナノ・マイクロレベルの生命現象を対象に、工学的手法を用いて生理現象の解明、生体操作、機能修復などを図る工学技術です。ナノ・マイクロレベルの生命現象として最も重要な対象は、細胞および細胞内の小器官、さらに細胞外マトリックスなど、長さの代表スケールが数10ナノメートル(ナノメートルは10億分の1メートル)から数100ナノメートルの構造とその機能です。個別の分子ではなく、生命のシステムとしての統合性が問題になるこのレベルでは、単なる化学反応ではなく、生命体の複雑な構造と機能が一体となって生命機能が維持されます。ナノ医工学では、このような認識のもと、具体的な臨床医学・医療への応用を視野に入れた生命現象の解明、構造の可視化と観測、治療的介入のためのデバイス開発、そして、これらの基礎技術を臨床応用する医療工学までを研究の対象範囲とします。
医工融合~医学と工学、その学際領域を総合し、新たな学術の地平へ。
ナノ医工学は、今世紀の科学技術の基調をなすキーテクノロジーになっていくものと考えられます。ナノ医工学分野を確立する鍵とは、多分野を総合し、新たな学術の地平を切り拓く医工融合にあります。さらに、医工融合を成功へと導くのは、世界最先端の研究を担うことを通じ、科学技術の光と影に思慮する感性と国際的な視座を涵養した若き“人材”に他なりません。
本グローバルCOEプログラム(以下、GCOE)は、21世紀COEプログラム(以下、21COE)「バイオテクノロジー基盤未来医工学」の事業を継承するものと位置づけられます。21COEでは「広範な領域を包括する医と工の融合分野である医工学を、バイオテクノロジーを軸として発展させ、世界的教育・研究拠点を形成する」という目標に向かって、着実に歩を進め、内外から高く認知・評価される活動を繰り広げてきました。その成果は、各賞の受賞実績にも現れています。
本GCOEでは、高度に機能している運営体制を承継し、有機的につながる国際ネットワーク構想をさらに盛り込んで、グローバルな教育・研究を可能とする体制へと進化・深化させていきます。
東アジア・環太平洋圏を主導するグローバルな拠点形成をめざして。

「東アジア・環太平洋圏」「欧米大西洋周辺地域」「ユーラシア」、これらは今後、ナノ・バイオ技術の発展を担うと考えられるエリアです。我が国は、東アジア・環太平洋圏の諸国・諸社会と緊密に連携し、もっとも成長ポテンシャルの高いこの地域を世界のナノ・バイオ技術の枢軸へと牽引していくことが求められています。
本GCOEでは、東アジア・環太平洋圏において確固たる科学技術上の拠点を形成しつつある諸国・諸大学と強固なリレーションシップを構築することを目的としています。そして、地域に根ざしてはいるが汎世界的な問題、たとえば、マラリアのような感染症の研究など、喫緊の課題から共通の医学的課題を抽出して協同の研究・教育に取り組み、医療を革新する体制を実現していきます。
人材育成のアクションプランとしては、21COEから継承する遊牧民的教育(Nomadic Education)と遍歴学生制度(Itinerant Studentship)に加え、ピアメンターシップ(Peer Mentorship)、国際メンターシップ(International Mentorship)とファカルティ・ディベロップメント(Faculty Development)を導入します。そして、これらを支えるグローバルe-learningシステムの具体的な運用を担当する実施チームを組織し、若手研究者に国際的経験を積む機会を潤沢に与えます。
人材を社会に還流させ、その人材による研究成果を世界に還元する ―― 本GCOEの取り組みが、ナノ医工学の劇的な進展をもたらす機動力となっていくことでしょう。
※さらに詳しい内容については、ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nanobme.org/
グローバルCOEプログラムは、大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際競争力のある大学づくりを推進することを目的とする事業です。2002年度から文部科学省において開始された「21世紀COEプログラム」の評価・検証を踏まえ、その基本的な考え方を継承しつつ展開されるもので、世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した世界最高水準の教育研究拠点づくりに重点的な支援が行われています。