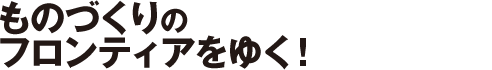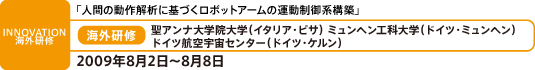研究分野の知見に加えて、
人に優しいヨーロッパの
街の姿を学ぶ。
心揺らした感銘は、
これからの研究の道を支える基に。
研究者として、夢と情熱を注げる研究テーマに出会えた人は幸せだ。修士課程からロボット工学の世界に飛び込んだ海隅さんは「介護ロボットの研究開発に携わりたい」と明快な目標を話す。その背景には、不幸にも病を得、要介護者となった祖父の姿があった。「介護する人の負担だけではなく、される人の心苦しさや抵抗感を軽減したい」といった具体性の帯び方は、現場に臨んだ人の視点に立脚している。福祉先進国である欧州に向かった海外研修、そこで海隅さんが見て感じたものとは?
大学院工学研究科 バイオロボティクス専攻
平田研究室
海隅 亜矢さん 博士課程前期1年
アメリカ留学で鍛えた英語も、研究発表の場面では勝手が違い…。

写真2 ミュンヘン工科大学で発表する海隅さん。
機械工学フロンティアの成果を基に研究交流をすべく向かったのは、聖アンナ大学院大学(Scuola Superiore Sant'Anna:SSSA)※1、ミュンヘン工科大学(Technischen Universität München)※2、ドイツ航空宇宙センター(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt:DLR)※3です。
高校時代の1年間、交換留学生としてアメリカで暮らしたという海隅さんをもってしても「難しい」と感じた英語での発表(写真2)。「準備段階から平田先生(工学研究科、バイオロボティクス専攻、准教授)にいろいろとご指導いただきましたが、日本語の説明をそのまま英訳すればよいというわけではなく、独特のプロトコルのようなものがあることを学びました」。そして、準備万端で臨んだ…つもりの発表でしたが「途中『ここはちょっと違うから、表現を変えよう』と思っても、機転がきかず頭が真っ白になりました」。また、質疑応答に際して、研究に対する掘り下げた質問を投げかけられたこともよい経験になったとも。「先方は、ストレートな解を求めていますから、まずは質問主旨をしっかり把握することが必要なんですね。でも、頭の中に回答があっても、すぐに言葉が出てこないところは閉口しました」。そして、類似性の高い研究の存在を知ったことも収穫のひとつ。「インピーダンス制御を用いて、バスケットボールのドリブルをさせるマニピュレータの研究をしている学生さんから質問を受けました。研究のフィールドはもはや世界なのだと、とても刺激になりました」。博士課程後期に進学することを予定している海隅さんにとって「研究者としての海外体験、その初めの一歩としてはとても充実したものでした」と大きな手ごたえを感じているようです。その目は、すでに将来を見据えています。