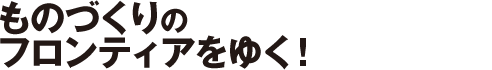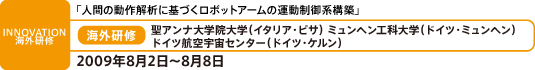研究分野の知見に加えて、
人に優しいヨーロッパの
街の姿を学ぶ。
心揺らした感銘は、
これからの研究の道を支える基に。
研究者として、夢と情熱を注げる研究テーマに出会えた人は幸せだ。修士課程からロボット工学の世界に飛び込んだ海隅さんは「介護ロボットの研究開発に携わりたい」と明快な目標を話す。その背景には、不幸にも病を得、要介護者となった祖父の姿があった。「介護する人の負担だけではなく、される人の心苦しさや抵抗感を軽減したい」といった具体性の帯び方は、現場に臨んだ人の視点に立脚している。福祉先進国である欧州に向かった海外研修、そこで海隅さんが見て感じたものとは?
大学院工学研究科 バイオロボティクス専攻
平田研究室
海隅 亜矢さん 博士課程前期1年
堂々と研究内容を語る、研修先の学生の勇姿が、これからの目標に。

写真3 SSSAにて。
「SSSAやミュンヘン工科大で研究室を見学させていただきましたが、研究テーマごとに部屋も厳密に区切られていて、学生個々が責任をもって担っている印象を受けました。もちろん真摯に研究に臨む姿勢は、本学も海外大学も全くかわりはないと思います。ただ本学の場合は、分野が異なっても同じ教室で、お互いに意見を交わしながら研究を進めるなどの横断的取り組みが顕著だと思います」。また、自身の研究について、自信をもって誇らしげに説明する研修先の学生の姿に感じ入ったとも。「ドクターコースの方々だったことを差し引いても、もし私が逆の立場だったら、こんなに堂々と自分の研究を説明できるだろうかと思いましたし、かくありたいという目標像が私の中に据えられました」。
将来は、介護ロボットの研究開発に携わりたい海隅さんにとって、研修地がヨーロッパであったことも幸運でした。「街のなかに車椅子利用者や杖に依っている人もいましたが、とても自然で無理のない印象でした。バリアフリーやユニバーサルデザインなど環境・設備の配慮が厚くなされているからなのですね。その光景は、社会のあるべき姿として記憶に刻まれました」。
海隅さんの豊かな感性は、研修先の大学や研究機関での学びにとどまらず、社会の有り様までをも捉えました。海外研修の成果は、学生の数だけ、多様な形で稔ると感じさせられます。「ぜひ後進にもこのような機会を」、有意義な経験を積んだ海隅さんからの要望も付け加えておきましょう。
取材日:2010年2月16日